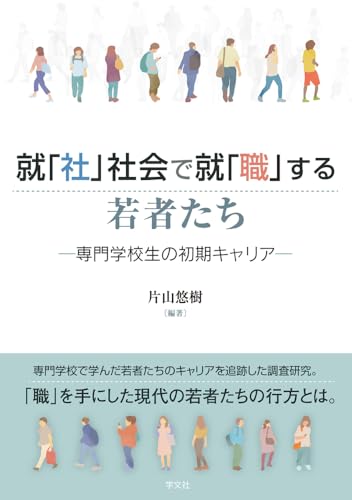本書では、専門学校卒の女性を事例に、職業教育の効果に対する学習者の語りを検討してきた。多くの先行研究では、職業教育の効果を計量的に実証してきた。そうしたアプローチから、職業教育のあり方を議論することは有効である。ただし、学習者が職業教育をどのように認識しているかという把握は必要であろう。そのため本書では卒業生の語りを検討してきたが、そこから導き出される知見は「知識の意味づけ」という視点である。
保育系専門学校の卒業生は、子どもの発達=「見えにくい」知識に対する重要性を認識するようになると、職業教育の効果を肯定的にとらえるようになる。ただし、そのためには、安定したキャリアという条件が不可欠である。
理美容系専門学校の卒業生の語りは、知識の用い方で分岐していた。美容関係の知識は「見えやすい」ものであるが、自身の施術のために知識が必要であると考える場合、教育機関で獲得された知識は陳腐化しやすいため、効果は否定的となる。一方で、知識を消費者のために使用する場合、学校で獲得した知識は基礎知識であっても有効と評価される。そのため、職業教育の効果は肯定的になりやすい。
専門学校卒女性の語りを辿ると、職業教育の効果は、どのような場面で知識をいかに使うのかといった、知識の使用方法によって左右される。職業教育の議論では、特定の仕事に有効な/必要な知識(あるいはスキル)や、知識の(学習者の)習得状況に焦点をあてられがちである。ところが、習得した知識を具体的な場面でいかに使いこなすかといった、学習者の「知識の意味づけ」について、必ずしも分析が進められてこなかったように思われる。文脈に紐づかない能力(コミュニケーション能力など)が特定の行為や内容をもたない「空虚」な訓練可能性になってしまわないように(Bernstein 1996=2000)、具体的な場面や使用方法とリンクさせない知識は「空虚」な知識となるのではないか。
(略)
本書では、学習者の視点から職業教育の効果を検討し、「知識の意味づけ」という観点の重要性を導き出した。今後は、この点も含めて職業教育の効果のメカニズムを検証することが必要であろう。
10章「専門学校卒の女性は職業教育の効果をいかに語るか?」
225-226頁
教育学における獲得された知識の活用への関心は必ずしも高いものではない(本書とはまったく異なる角度でその状況を批判したのがパウロ・フレイレである)。研究が行われる場合であっても、民主的な政治への参加や普遍的な人権に関する実践のような「商売」から離れたテーマが選ばれてきた傾向がある。本書は職業の実践が行われる場面に着目して、学習の当事者にとって獲得された知識がどのような意味をもつのか、また、その意味を支える外形的な条件は何かを検討するという、極めて重要な課題に取り組んでいる。
それぞれの章もとても勉強になった。とりわけ、6章「専門学校女子学生の性別役割意識の変化」では、専門学校在学中に性別役割意識が高まる理由についてデータに基づいて考察している。専門学校の機能は職業的社会化に一元化されているわけではないという先行研究の指摘どおりに、学習者の価値観や規範意識へ及んでいる。また、本文中に使われている言葉ではないのだけれども固有の「隠れたカリキュラム」も存在していそうである。一つの立場からすれば矛盾を生じさせるはずの職業教育と性別役割意識の関係は、Bernsteinを使うのであればID/RDで説明できそうもある。また、8章「キャリア形成と地域移動―保育系と美容系における仕事と地域」も勉強になった。若者の地域移動研究(≒移動しない研究)には優れたものが数多くあるものの、就いている職業やその職業に結び付くライフコースの展望を変数に入れることによってさらに理解が深ますのである。メイク系、アイリスト系、美容師のそれぞれにやや違いはあるものの都会への移動志向、キャリアアップ志向、独立開業などへの関心はかつて教育社会学で盛んに行われていた日本型立身出世主義(イデオロギー)研究を思い出させる。一方で「見知った」土地での勤続を願う保育系は若者の「地域移動しない研究」に接続するものであり、それぞれのライフコース「戦略」が浮かび上がっている。
二宮がもっとも興味をもったのは5章「職業教育と非認知能力―説明能力に注目して」である。
本書の目的は、自動車整備士系専門学校を事例に、職業教育を通じた非認知的能力の教育可能性を議論することである。具体的には、「説明能力」に注目し、職業教育の中で「説明能力」がどのように位置づけられ、教育されているのかを試論的に考察する。
教育研究において、能力は重要な関心領域である。1960年代には、経済発展に資する教育計画論(マンパワー政策)に対する批判が教育研究の中で展開されたが、焦点のひとつが能力であった。1990年代に入ると、能力議論は再び活況を迎える。その特徴は、能力を多元的に分離してとらえようとすることである。例えば、「キャリア発達に関わる諸能力」(人間関係形成能力、情報活動能力など)や「社会人基礎力」(前に踏み出す力、チームで働くなど)など、さまざまにネーミングされた非認知的能力に注目が集まり、政策を通じて育成の重要性が主張された。
こうした議論に対する反応は、大きく二つに分けることができよう。ひとつは、諸能力の内実を子細にリサーチし、教育実践に落とし込む=「飼い慣らす」ことを目指すアプローチである。松下佳代(2010)や白井俊(2020)がその代表である。もうひとつは、分離された能力に対して疑問を呈するものである。本田由紀(2005)は、「能力の多元化」は手続き的公正を蔑ろにする危険性を有すると主張している。また、中村高康(2018)は、コミュニケーションや柔軟性といった能力は必要ではあるものの、決して新しい能力ではないと指摘している。能力議論の言説構成を俎上に載せ、能力を理解することに対して慎重さを求めている
本書では、上記の2つのうち、前者の立場から議論を展開してみたい。このように書くと、松下などの主張に同調しているように見えるが、ここでの目的は能力の多元化や非認知的能力の新しさを主張することではなく、能力概念の背景を踏まえながら、位置づけられ方や特定の条件下での教育可能性を議論することである。具体的には、「キー・コンピテンシー」を事例に、1970年代に登場したコンピテンシーとの違いを「職務」という視点から確認する。そのうえで、「説明能力」を題材に、非認知的能力とはどういった文脈で必要とされるようになったのか、そして職業教育を通じて教育可能であるのかを検討する。
5章「職業教育と非認知能力―説明能力に注目して」
94-95頁
かつて「職人」であった技術者は技能者は確かに他人、特に顧客とコミュニケーションをする必要がなかった。厳密に言うとその必要はあったのだけれども「職人気質」という言葉で説明されるようなコミュニケーションの作法が通用していた。「言葉は悪いけれども腕は立つ」「寡黙であることこそが職人の証である」ことが認めらていた。他方、本章でも説明されているように、現代ではたとえば自動車整備士が「消費者からの納得を得る」(101頁)ための「説明能力」を身につける必要がある。その事実認識や、その教育可能性を問うことの重要性についてはとても納得できることであるし、大学の理工系学部や医療系学部において「高度に専門的な知識を一般向けににわかりやすく説明できるようになろう」と主張されることがあるのも聞き及んでいる。社会のサービス産業化というような概念で把握されてきたことでもある。また、結論として挙げられている「非認知的能力を教育可能なかたちにするためには、一定の文脈が必要である」(113-114頁)というのもその通りであり、かつてBernsteinが批判していた論点から(日本を先取りするかたちで進んでいた英国の教育政策(のあまり成功しなかった部分))も導かれることであろう。たとえば、日本の大卒ホワイトカラーに関しては、リクルート社のコミュニケーションと大手都市銀行のコミュニケーションは明確に異なっているはずなのだけれども、それぞれの文脈を無視したかたちで「汎用的コンピテンシー論」が流通していたのである。なお、111頁の表5-4「説明能力の規定要因分析(多項ロジスティック回帰分析)」はとても面白かった。日本の「汎用的コンピテンシー論」でよく主張されていた「サークル・クラブ活動の参加」や「アルバイト経験」は、「説明能力」の自己評価(自身あり、および、自信アップ)に対してほとんど有意ではない。あくまでも自己評価ではあるものの、有意である変数は「座学の成績」と「実技の成績」である。専門的な分野の成績こそが主観的な「説明能力」に影響を与えているのである。
この5章に関して論点を2つ挙げてみる。1つは、「説明能力」についてである。二宮の読み込みが不足しているかもしれないが、ここでは2種類の「説明能力」が提示されているようにみえる。まず、自動車の整備内容に対する専門的な説明の能力である。これについては「職人」も行っていたかもしれない。整備を依頼した消費者にとってはまったく理解できない内容であっても、「職人」はそれを説明したのだから十分である。次に、自動車の整備内容にする専門的な説明を通じて、消費者を納得させる能力である。おそらく、この能力こそがサービス産業化した社会で必要であるとして流通されるものである。調査設計上の難しさから、この「お客様は神様です」言説に依拠した能力自己評価については捉えることができていない。「汎用的コンピテンシー論」に回収されることがないという前提のうえでの技術や技能よりも先立ってしまうような「説明能力」についてて、どのように把握すれば良いだろうか。もう1つが提案された「職務コンピテンシー」と「教育コンピテンシー」の関係についてである。前者は心理学・経営学由来の職務または状況依存的な卓越した業績に関する個人の特性というコンピテンシーである。日本の企業における経営実践においても、当初はこの「卓越」に関心があった。そして、後者は職務という文脈が外されたものであり、「卓越」や「個人の特性」という観点は等閑視されている。この2つの違いは経営実践に対しても混乱を招いていて、(リクルート社が発行するような)HR系の雑誌などでもたびたび話題にされてきた。そこで、「職務コンピテンシー」の「教育化」や「脱文脈化」が生じる理由についてもう少し説明が必要であるように思われるのである。ある知識が伝達・教育の対象となるとき、それはもともとの知識そのものではなくなるということは教育社会学としては自明であるとはいえ、それが現代の専門学校や大学で生じるメカニズムについて検討する課題(検討対象は知識ではなく能力であることがとても難しい)が残されていそうである。また、筆者も論点として十分に把握していると思われることなのだけれども、「教育コンピテンシー」が教育可能であると認識されてしまう理由についても考えてみたい。文脈のないコンピテンシーについて、どんな専門家がどの順番でどのように教えることが可能であるという共通の了解が生じることなどについての知識社会学的な研究が可能でありそうなのだ。