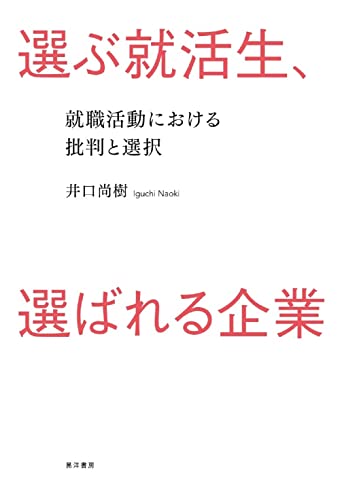本書は、以下の2つの見方を相対化する。第1に、採用・就職活動は、学生が志望を先に決めた後は企業が学生を一方的に選抜する場であるという見方(一方向的選抜図式)、第2に、「人物評価」はメリトクラシーの理念をより忠実に反映した選抜のあり方で、それゆえ人々からの批判が生じない(選抜をされる者は無力な被害者である)という見方である。
p.9
本書は、少なくとも日本の大卒就職の事例における応募者の反応のあり方を正確にとらえる上では、「被選抜者」としての側面だけでなく、批判や選択を行う側面をみる必要があることを主張するものである。それは、(本田も描こうとした)竹内以後の日本のメリトクラシーのあり方を考える上でも、また(Sharoneらが取り組んだ)現代の「劣等」感情の社会的要因を考える上でも、重要なカギとなるというのが、本書の見立てである。
p.14
そのうえで、就職活動を経験した大学生を対象とした聞き取り調査のデータに関して、たとえば、先行研究の枠組みを援用して就職活動は次に示す「ゲーム」の重なりであると認識されているという解釈を示している。評価基準が学校歴や専攻などである「スペック・ゲーム」、採用担当者との相性のような「ケミストリー・ゲーム」、部下・後輩という規範についての「従順ゲーム」、志望意欲の高さの「コミットメント・ゲーム」、特定の課題を解決できる「スキル・ゲーム」のそれぞれに対して、大学生によるゲーム対策としての「戦略」やゲームの正統性についての判断を考察している。「ケミストリー・ゲーム」では面接の時間や内容に偏りがあったり、「従順ゲーム」では演技によって採用担当者を騙せたりすることから、その正統性を疑うことが可能なのである。このように先行研究では実証されてこなかった、唯々諾々と「ゲーム」に参加させられるというわけではない学生の能動的な判断の特徴を明らかにしているのである。このことは、教育社会学者の本田由紀が示す「抵抗」の側面としても位置づけられるものである。
私(二宮)が示すことのできる論点が4つある。(1)まず、時代背景とメリトクラシー観の関係についてである。竹内洋によるそれ以前の「(雇用されて働く男性の)立身出世イデオロギー」を背景とした1980年代におけるライフコースの各段階におけるメリトクラシー、本田由紀による主に就職氷河期やその氷河期の感覚を社会的に引きずり続けた時期におけるメリトクラシーに関する実態及び社会的な認識と、本書が対象としたポスト就職氷河期(と断定してよいのかわかならいけど)におけるその実態及び社会的な認識の違いを示すことができると、就職活動を行う大学生の現代的な特徴をより際立って明らかにできるのかもしれない。教授・研究室推薦が行われた世代や就職氷河期の世代からすると、本書で描かれているような大学生が「(かつてより相対的には自由に就職先を)選択できる」という視点は新鮮なものであり、選択できるからこ困難があることじたいが興味深いのである。(2)次に、メリトクラシーそのものについてである。本書は社会学によるアプローチであるため、メリトクラシーを研究対象とすることの意義が教育社会学や教育学とは異なっている。メリトクラシーじたいを理念的、批判的に考察したり、メリトクラシーに見えるものが実際には家庭の資本を使うものにすぎないペアレントクラシーであることを明らかにしたりするような研究とはまったく違う関心をもっているようにも見える。しかし、既述の「竹内以後の日本のメリトクラシーのあり方を考える」というねらいがあるとするならば、この分野毎のメリトクラシーへの関心の持ち方に由来する思考の特徴についての整理が必要なのであろう。(3)そして、「マッチング」の意味についてである。これは私が先行研究についての勉強不足のために生じている単純な疑問であるかもしれないものの、「マッチ」とはどのような状態を指すのかが不確かであった。その意味の確定を一端止めてみるとしても、本書も終章で指摘しているとおり「マッチ」の精度を高めようとすると時間的、経済的コストが跳ね上がる。また、いわゆる「ジョブ型」ではなく「メンバーシップ型」雇用慣行のもとでの「マッチ」は容易に正統性の怪しさを指摘できる「ケミストリー・ゲーム」や「従順ゲーム」にならざるを得ないかもしれない。さらには、大卒3年以内の早期離職者の割合は1970年代から景気にかかわらず継続して3割程度であり(もちろん企業規模による違いはある)、それは個人や個別資本としてはどうすることもできない社会の「構造」や「システム」の問題として捉えられるのかもしれない。この早期離職率の変わらなさは教育社会学よりも、むしろ社会学の検討課題であろう。また、「マッチ」するように求人側、求職側も努力せよということではなく、(定義次第ではあるものの、なにかが)「ミスマッチ」であっても働き続けられるようにしたり、あるいは、3割程度の早期離職率を当然の前提として見込んだうえで「ミスマッチ」の場合の転職を促すという方針を取ったりすることも実行可能な方針である。いずれにせよ、求人と求職の「マッチ」とはそれほど簡単に理解できるような概念ではない。(4)最後に、「一元的序列」についてである。この概念が使われているものの教育学者の乾彰夫が引用されているわけではなかった。学校と労働とを貫く「一元的序列」の生成過程については、乾彰夫『日本の教育と企業社会――一元的能力主義と現代の教育=社会構造』で明らかにされてきた。本書では、大学生は就職活動を経験する中で「一元的序列」と合わせて「多元的序列」の存在を認識するという。それは確かに当事者の大学生の実感としてはそうであるものの、乾などが指摘してきた「多元的」というのは今でいう「ジョブ型」雇用に近いものなのかもしれず、また、新卒採用が制度化されたうえで「訓練可能性」や「職務遂行能力」という抽象的な「能力」が重視されたことじたいに「一元的序列」の特徴を見出していたのかもしれず。そうだとするとこれらの概念の再整理が必要になるだろう。